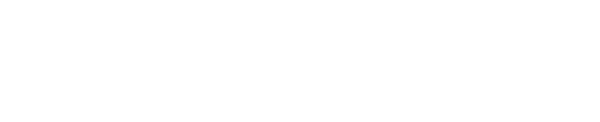ビジネスは思想に傾倒せず、観察に徹する
リベラリズムの光と影──日本的再定義のために
リベラリズムとは「自由を思いのままにとらえる」思想である。だが、その自由は必ずしも中立的な光ではない。ときに伝統や共同体の基盤を切り崩す刃物として作用する。1970年代以降、欧米から輸入されたリベラルフェミニズムや人権運動は、自由・平等・正義を拡張し、人間の尊厳を守ると同時に、家族制度や国家の統合を揺さぶり続けてきた。その波は日本社会にも届き、戸籍制度や家族観、さらには天皇制にまで影響を及ぼす可能性を孕んでいる。
米国の戦略家ブレジンスキーは、冷戦期に「戦略的リベラリズム」を武器として活用した。自由や人権を掲げながら国家を分断し、内部対立を深めることで統治を弱める。これは単なる理念の輸出ではなく、実際に国家運営を揺るがすための政治的手法であった。リベラルな価値観が善意の普遍思想であると信じるのは危うい。むしろそれはしばしば「外圧」として機能し、受け入れた国の社会構造を変質させてきた。
自由は光である。しかし、孤立した権利の拡張に傾けば、人心を疲弊させ、共同体を弱体化させる。民主主義とピューリタニズムの二重性を持つアメリカ型リベラリズムを無批判に輸入するのではなく、私たちは日本独自の文脈で「自由」を再定義する必要がある。縄文以来、多様な人々を受け入れつつ同化を促し、一体性を育んできた日本の歴史には、自由と伝統を調和させる知恵が刻まれている。
切断された自由は混乱を生む。しかし調和の中に位置づけられた自由は、安定と創造を育む。これからの日本に必要なのは、輸入された概念に翻弄されることではなく、伝統と共同体を基盤にしながら自由を広げる「日本的リベラリズム」の探究である。それは国家を弱めるのではなく強め、人心を分断するのではなく結び直す方向へと導くだろう。今こそ私たちは、この国にふさわしい自由のかたちを問い直す時にある。