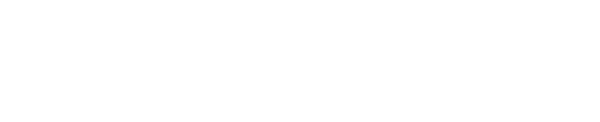財政法第4条の呪縛
【占領政策の呪縛からの解放】
〜財政法第4条と財務省の誤謬が日本の未来を閉ざす〜
日本の国家運営は、いまだ「占領時代の呪縛」の中にある。
その象徴こそが、1947年(昭和22年)3月31日に制定された「財政法第4条」である。
⸻
■ 財政法第4条(正確な条文)
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
ただし、公共事業、出資金及び貸付金の財源については、**国会の議決を経た金額の範囲内で、**公債を発行し、又は借入金をなすことができる。
この場合においては、償還の方法をあらかじめ国会の議決を経なければならない。
⸻
■ 占領下で刻まれた“金科玉条”
この条文の根底には、敗戦国・日本を軍事的・財政的に無力化するための「占領政策」の意図が込められていた。
つまり、政府の自由な財政支出(=主権的通貨発行)を封じ込める仕組みである。
それが今日に至るまで、「財政均衡原理」という誤った倫理観とともに、日本の政策中枢に棲みついている。
⸻
■ 財務省の病理と思考停止
財務省はこの条文を錦の御旗として、財政支出を極端に制限し続けている。
その結果、日本では次のような国債の「誤解された運用」が定着してしまった:
• 建設国債(1966年〜)
• 特例国債(1965年〜)
→ いずれも 「60年償還ルール」 という、他国に存在しない“返済原則”が制度化された。
これにより、国債はあたかも「必ず返済しなければならない民間の借金」であるかのように扱われるようになり、「国の借金が膨らめば国家が破綻する」という誤った観念が国民全体に刷り込まれていった。
⸻
■ 国家は家計でも企業でもない
国家は「企業」や「家庭」とは異なる。
なぜなら国家には、次の二つの財政上の主権があるからだ。
1. 徴税権(Tax Sovereignty)
2. 通貨発行権(Monetary Sovereignty)
この二つを併せ持つ限り、政府は「通貨を発行して支出し、必要に応じて課税で吸収する」という行為が可能である。
つまり「支出が先で、税は後」。これが**主権国家の財政の原則(Spending First)**である。
⸻
■ 「ギリシャのように破綻する」の誤解
よく引き合いに出されるギリシャとの比較も誤りだ。
• ギリシャはユーロ加盟国であり、通貨発行権がない。事実上、自国通貨を持たない地方自治体と同じである。
• 日本は円という自国通貨を発行でき、国内債務が中心。ゆえに破綻の前提が根本的に違う。
つまり日本政府は、自国通貨を持たない国家と同様の“思考回路”で政策を行っているという、本末転倒の状態にある。
⸻
■ 60年償還ルールは企業会計的な錯覚
国債の「60年償還ルール」などは、もはや企業の減価償却と変わらない。
しかし国家は、企業のように損益計算や黒字決算を義務づけられている存在ではない。
必要なのは、インフレと資源制約に配慮した上で、適切に通貨を発行し、経済を動かすことである。
⸻
■ 日本の未来を取り戻すには
いま必要なのは、次の3つの「覚醒」である。
1. 占領政策の遺物=財政法4条の再構築
2. 国家と企業の本質的な違いの理解
3. 「税と国債の順序」の再教育(支出が先、税は後)
これらを実行するには、財務省の思考停止を打破し、通貨主権を正しく理解する政治家と官僚を登用することが不可欠である。
⸻
■ 結語
国家が「経済成長に支出できない」ことこそが最大の亡国政策である。
もはや戦後ではない。
だが、日本の財政思想はいまだに「戦後」なのだ。