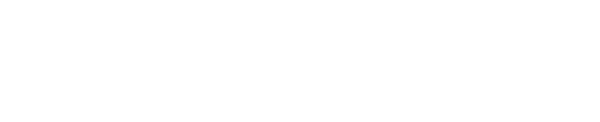日本人の生き方
誰かと語り合い、手を取り合い、笑い合う。
そんなささやかな営みが、
この国の未来をもう一度立ち上げるかもしれません。
絶望せず、淡々と、しかし確かに。
“お天道様の目”と“いまここ”のまなざし、
その両方を胸に抱いて。
お天道様と戦国の記憶──國體と絶望のあいだで
「人生には、二つの視座がいる──
一つは空のように遠く、もう一つは足元の土と共に。」
現代社会を生きる私たちにとって、「視座」の取り方が問われる時代になりました。
そのひとつは、“永遠のまなざし”。
哲学者バールーフ・デ・スピノザが語った「永遠の相(エターナル・アスペクト)」、
これを日本の感性で言い換えるならば、「お天道様の目」となるでしょう。
五百年、千年の時を見渡し、国や文明、人間の営みの栄枯盛衰を静かに見つめる視点です。
そしてもうひとつは、“いまここ”のまなざし。
目の前にいる誰かの体温や呼吸、言葉の余白に耳を澄ます視点。
手を取り合うように関係を築く、足元の温かさを見逃さないまなざしです。
この二つを併せ持つことこそ、人間らしい生き方。
ところが現代人は、どちらか一方に囚われがちです。
未来や過去ばかりを論じる者は、日々の対話を失い、
「今ここ」に埋没する者は、時代の大きな流れに飲まれていきます。
人生は一度きり、百年も生きられれば御の字です。
ならば、せめて正直に、心地よく、幸福に生きたい。
その第一歩は、崇高な理想論でも啓蒙でもありません。
「誰かと丁寧に向き合うこと」。
誰かと真剣に関係を築けない人が、
国や政治を語り始めると、話は宙に浮いてしまう。
人との所作を軽んじる言葉は、
どこまでいっても「空中戦」にしかならないのです。
そんな時、ひとつの問いがふと浮かびます。
──「応仁の乱」って、どう思う?
室町末期、1467年。
応仁の乱は、日本の中央政権が機能不全に陥り、
戦国時代が幕を開けた象徴的な混乱でした。
京都は焼け、武士も民も将来の見通しを失った時代。
まさに「國が壊れる」と思われた瞬間だったでしょう。
しかし人々は、それでも生きました。
耕し、味噌を仕込み、唄を詠み、子を産み、祈ったのです。
混沌のなかにも日常は息づいていた。
さて、いまの私たちはどうでしょうか。
戦後80年。
平和と経済成長の果てに、
私たちは氣づかぬうちに「國體」というものを
少しずつ静かに、形骸化させてきたかもしれません。
國體とは何か?
それは法や制度ではなく、
もっと素朴な「つながり」の総体であり、
日々の営みのなかに滲む、この國のかたちです。
けれど、希望はまだ残っています。
地方には、いまも「産土神(うぶすながみ)」のような、
土地と人の結びつきが生きています。
目には見えなくとも、根は確かにそこにある。
絶望に飲まれないために、必要なのは
500年の視座と、今日の小さな一歩を併せ持つこと。
大きな時代を見渡しながら、
今日という日を丁寧に歩むこと。
それが、この國の「根っこ」の力を信じるということなのです。