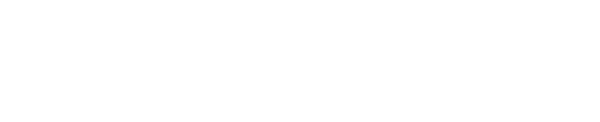「借金は通貨の母である」
借金は罪か、それとも希望か
――お金と信用創造、そして国家財政の誤解を撃つ
お金の本質は何か。長らく「物々交換の代替物」と教えられてきたが、それは神話に過ぎない。歴史が示すのは、お金の起源が「借金の記録」であったという事実だ。古代メソポタミアの粘土板に刻まれたのは物の価格ではなく、貸借の約束。つまり、お金とは誰かの負債であり、他者にとっての資産――信用そのものの記録なのである。
現代においても、銀行が融資を行うたび、新たな預金が「無」から生まれる。これを信用創造という。お金とは、実体ではなく構造物。借金がなければ、経済を流通する通貨そのものが存在し得ない。
ところが日本では、「借金=悪」とする道徳観が教育や社会通念に深く染み込んでいる。これは家計簿道徳を国家運営に持ち込んだようなもので、財政赤字を「国の借金」として忌避し、支出を切り詰める風潮を生んできた。
だが、国家財政の本質は異なる。政府はお金を「徴収して配る」のではない。支出(Spending)が先、税収(Taxation)は後というのが、主権通貨を持つ国家の基本原理だ。政府はまず通貨を発行して社会に支出し、その後に税金で一部を回収している。つまり、支出がなければ経済にお金は流れない。国民の貯蓄や企業の利益、すべては政府の赤字によって生まれる黒字なのだ。
ゆえに、財政赤字を単なる「ツケ」と見なすのは誤りである。むしろ、将来への投資――教育、医療、インフラ、技術開発――こそが健全な「未来への前借り」であり、賢い借金だ。
借金とは破滅ではない。それは通貨の起源であり、社会の血液であり、未来を拓くレバレッジである。
お金が存在する限り、借金は罪ではない――それは、希望そのものだ。